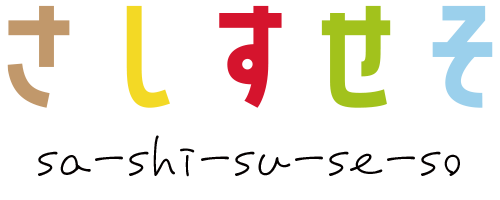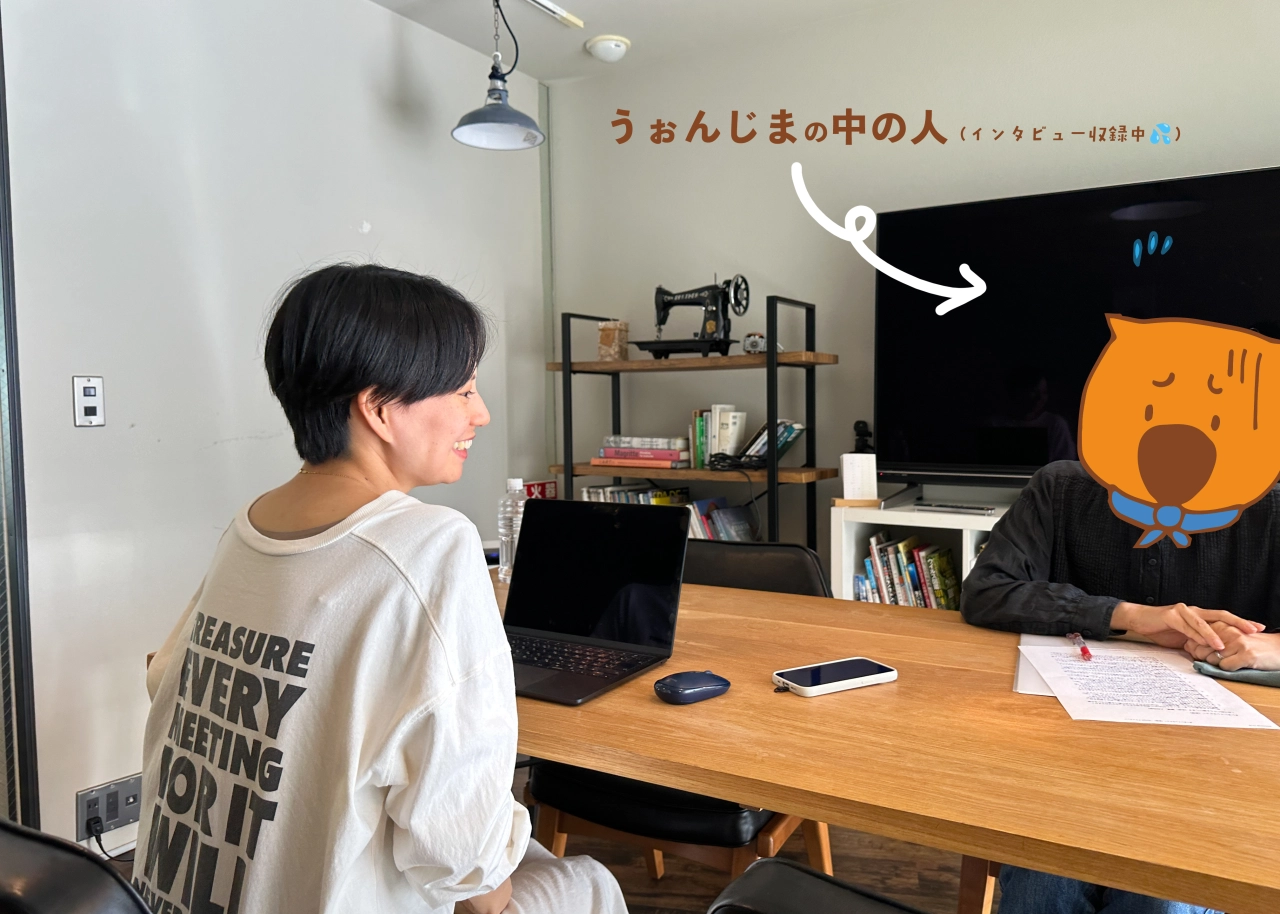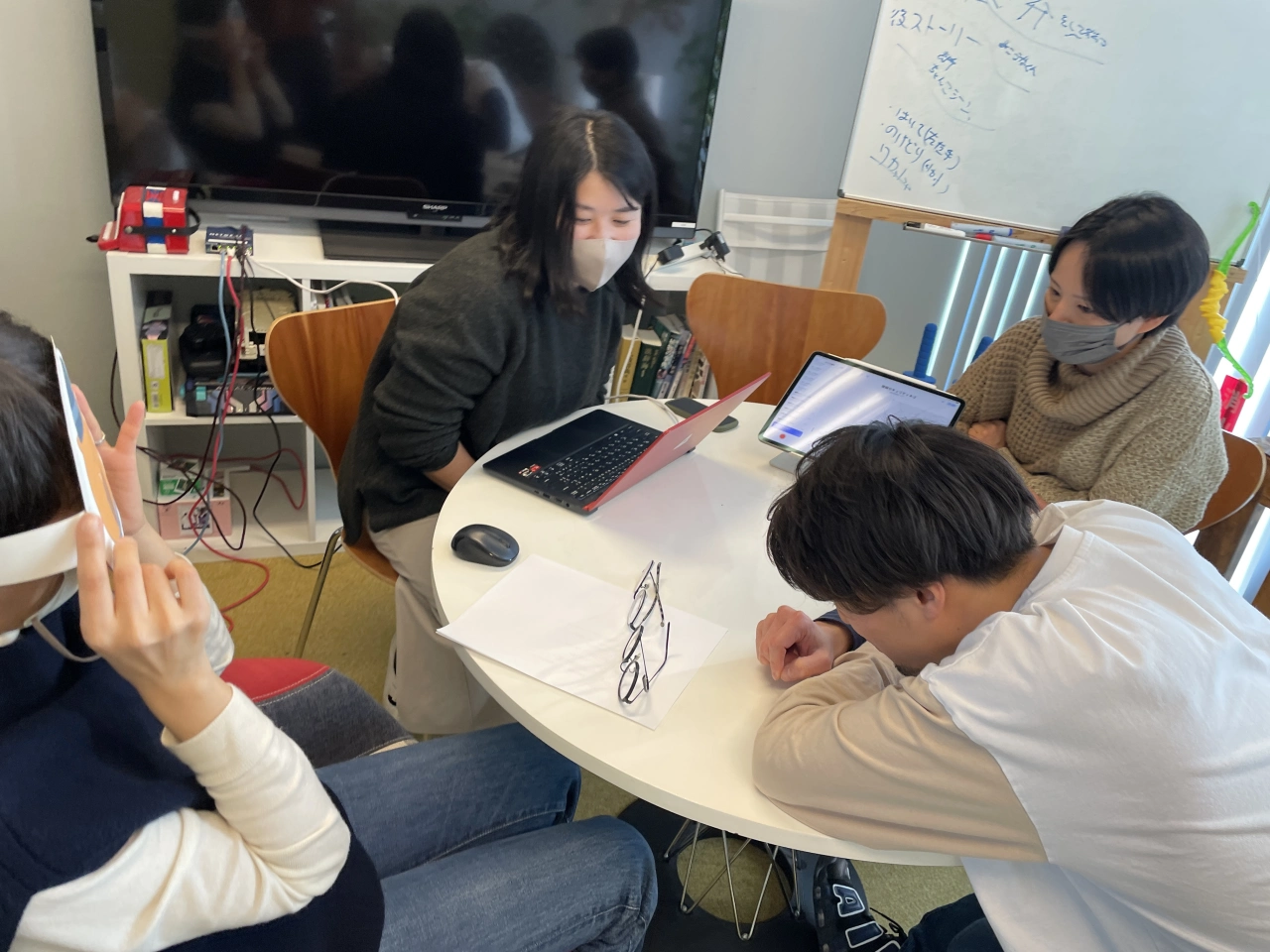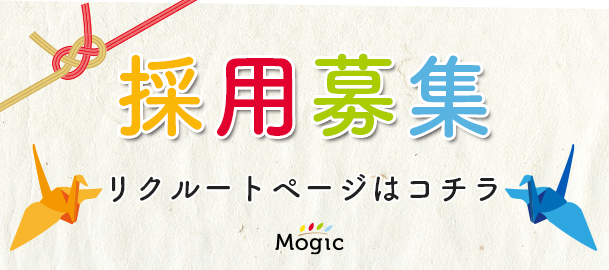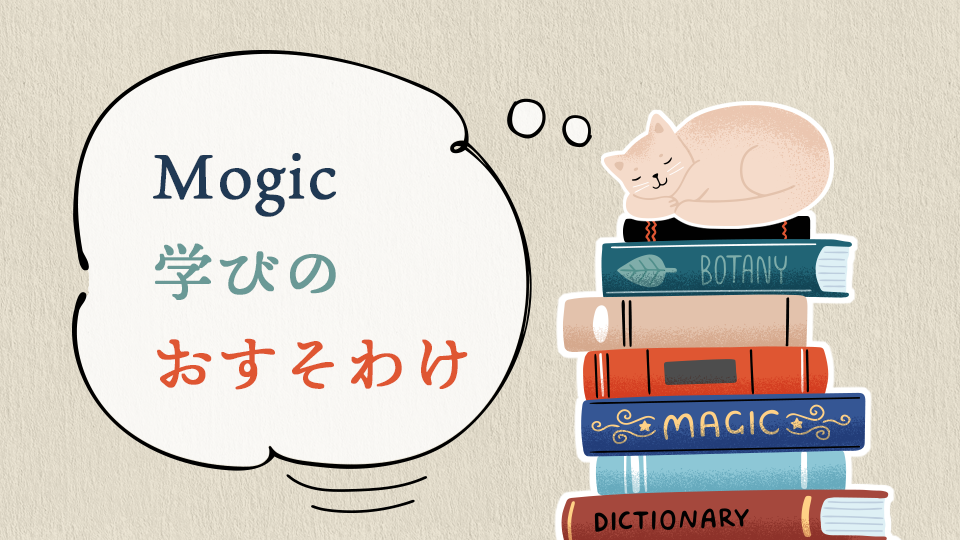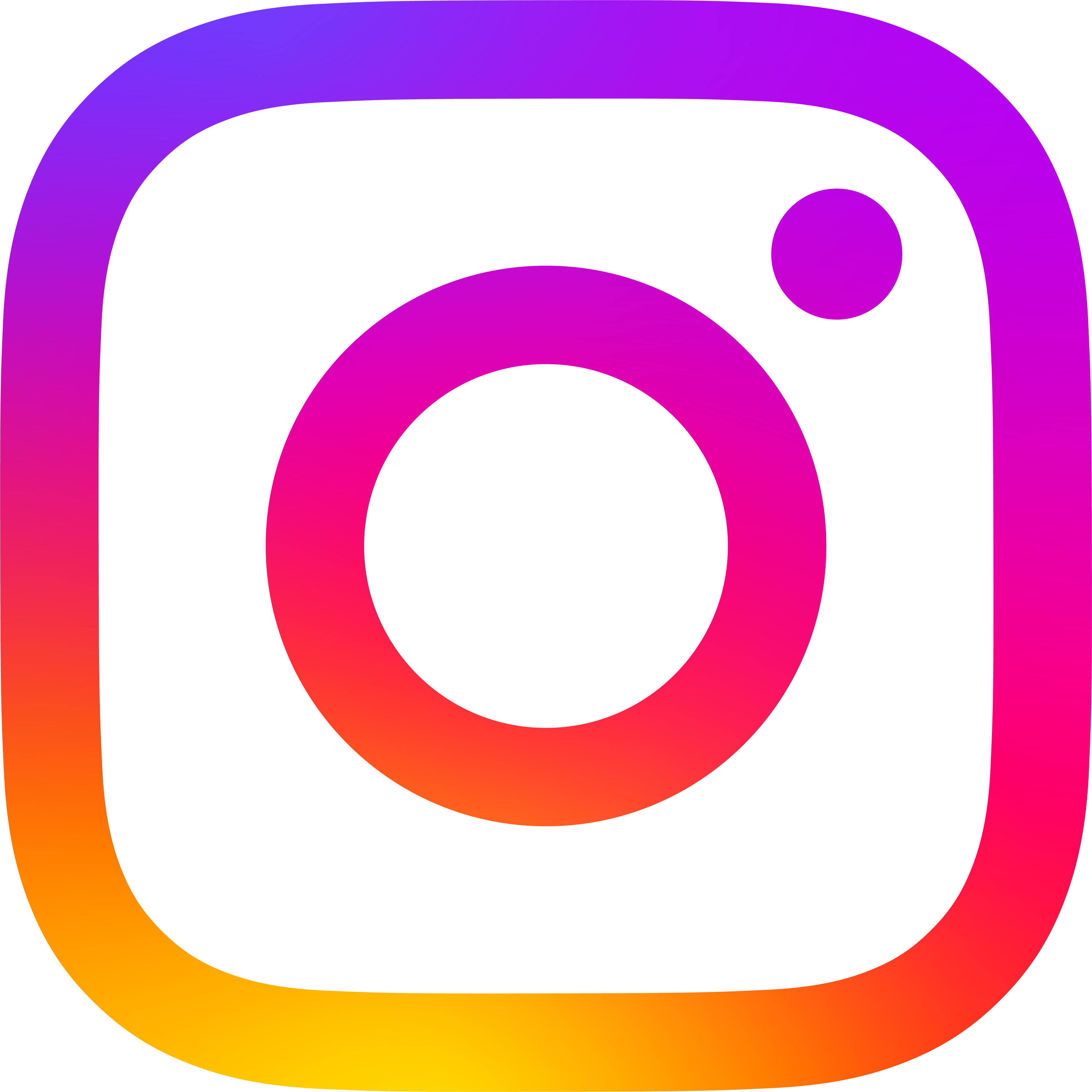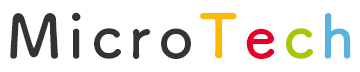「また整形作業か…」そんなため息が聞こえてきそうな作業が、この数か月でガラリと変わりました。
KOMADOの社内インタビューやアンケートの運用で、生成AIを本格的に取り入れ始めたのです。でも、ただ楽になったという話ではありません。「効率化しつつも、Mogicらしさを残す」という、なかなか絶妙なバランスを探る日々をお届けします。
作業フローの見直しから始まった
以前の流れはこうでした。インタビューを録音して、外部の方に文字起こしをお願いし、戻ってきたテキストを読みやすく整形して、最後に入稿用のマークアップ。特に整形とマークアップの部分で時間がかかっていて、「この工程、もう少し効率化できないかな」と思っていたのが正直なところでした。
生成AIを導入してからは、整形作業が格段に早くなりました。そして何より、マークアップの知識がなくても瞬間的に入稿用の形にできるのは本当に助かっています。
でも、ここで終わりではありませんでした。
「素材を活かしたい」という思い
効率化できたのは嬉しいのですが、同時に気になることがありました。生成AIで処理すると、どうしても文章が均一化されてしまうのです。話し手の独特な言い回しや、ちょっとした間、そういった「ざらつき」が消えてしまう。
でも、KOMADOで大切にしたいのは、まさにその「手触り」なんです。
だからこそ、生成AIを使う時は「素材を活かす」ことを意識しています。話し手の個性や、その人らしい表現を残しながら、読みやすくするにはどうすればいいか。完全に任せるのではなく、「Mogicの色やノイズが消えないように」調整を重ねています。
広がる活用範囲
制作プロセスの見直しから始まった生成AI活用ですが、今では色々な場面で使っています。
お知らせの作成、企画のアイデアを叩き台として可視化、アイキャッチの作成、記事づくりのフォローアップと入稿作業。インタビューの質問も、事前にフィードバックをもらったり、足りない視点を補填してもらったりしています。
つまり、制作プロセスの様々な場面で、ちょこちょこと活用しているのが現状です。
「楽になった」だけじゃない話
でも、これは単純に「楽になった」という話ではありません。生成AIを使うことで効率化できた分、他のクリエイティブな作業により時間を使えるようになったのです。
整形作業にかかっていた時間で、新しい企画を考えたり、インタビューの質を高めるための準備をしたり。結果的に、コンテンツの質が向上している実感があります。
日々のブラッシュアップ
そして何より、この効率化も「日々のブラッシュアップ」の一部だということです。
「今日はこの作業がもうちょっと楽にできないかな」「このプロンプトをもう少し調整してみよう」そんな小さな改善を積み重ねています。
完璧なシステムを一度に作るのではなく、使いながら少しずつ良くしていく。これも、私たちらしいやり方なのかもしれません。
ものづくりの新しい風景
生成AIという新しいツールが加わったことで、ものづくりの風景が少し変わりました。でも、大切にしたいものは変わっていません。
人の声を大切にして、その人らしさを残しながら、より多くの人に届けやすい形にする。そのために、新しいツールも活用していく。
きっと、同じような課題を抱えている人も多いはず。完璧を求めすぎず、でも手触りは残したい。そんな気持ちでものづくりを続けている人たちの、ちょっとした参考になれば嬉しいです。